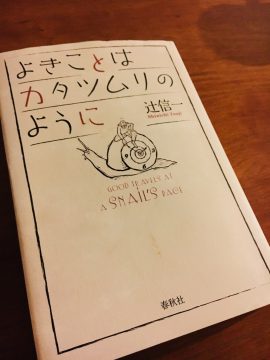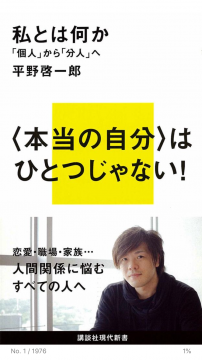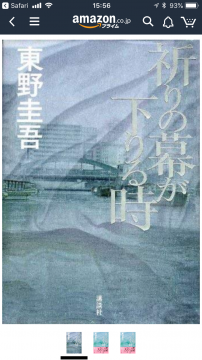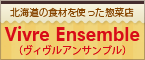講習会と試験に横浜へ。
開港記念館という素晴らしい建物の中に一日中缶詰です。
この安心安全安倍自民党独裁国家の日常生活において、銃の必要性など全く必要のないのにわざわざ持ちたい人なんて、
私も含めてちょっと気がふれてるアウトロー人間やサバゲーヲタクのようなキレたら何するかわからないようなヤバイ奴など、
目が合わないアブナイ人がさぞや沢山の来て、警察に対抗心燃やして椅子から脚を出して腕組みしながら野次飛ばすような、例えるならばガチンコファイトクラブみたいなのを予想、期待してたんです。
生徒がガチンコファイトクラブみたいな、ならず者ばかりならば、
講師も竹原みたいなドスの効いた広島弁のコワモテで、
銀縁のサングラスでもしてきてくれれば
私的にも非常にネタとして面白かったんです。
おい!テメーら、銃ナメんな!
みたいな。
が、完全に期待を裏切られて、講師は初老の紳士、公安はエリートっぽい七三わけの弱そうなお兄さんで、受講者はいたって普通の人ばかりでした。
この後鉄砲屋さんに行って買いたい銃買って弾を買えば、バンバン撃てるわけではありません。
銃も色々と種類があって自分のやる事に対して最適なモノを選ばなくてはいけません。
この後、射撃場での実射訓練と試験があり、それに通ると公安の身辺調査が入り、医者の診断が入ります。
オタクの旦那、犬に対するDVとか犬に対する過度の可愛がりとか犬に対する高圧的なネッチョリした言動とかないですか?
オタクのシャチョーの荻野さん、スタッフに対して罵声とかセクハラ言動とかドロップキックとかヘッドバットとかないですか?
オタクの旦那、遅い車に乗ってるから高速道路でプリウスやアルファードに後ろから煽られたり、無理な追い越しされて舌打ちした後に追跡したりしないですか?
などなど。
あとは罰金刑含む犯罪歴などを照合して所持許可が出されます。
私の場合、スピード違反と駐車禁止ですね。
血だらけのイノシシ積んで職質かけられた時は罰金も無かったし。
その後も所持している弾の数と撃った弾の数が合わなかったりすると逮捕されたり、いきなり警察が家に来て保管状況の確認したりと、まあ面倒な事が盛りだくさんです。
それにしても日本の銃規制は本当に厳しい。
まあ、必要のない危険物を所持するわけですから、厳しくて当たり前です。
アメリカでは小学校で銃の取り扱いについて学ぶことが基本で、オモチャの鉄砲はおろか、
水鉄砲ですら、人に銃口を向けることに対して絶対にしてはならない、そして引き金に指をかけることの意味合いもしっかり学ぶのだそうです。
なぜ厳しい銃教育なのに乱射事件など起きても厳罰化や規制がかからないのかについては、この講習をキッカケに私なりに考えました。
それはまたの機会に。
私の場合、狩猟が趣味というわけでもなく、単純に銃を撃ってみたいという奇形した嗜好もありません。
食べ物を食べるという事の背景とプロセスを徹底的に自分ごとにしたいというだけです。
ならば、釣りでも畑でもいいでしょう。息子がもう少し大きくなったら一緒に釣りに行って魚を釣って食べるでしょうし、うちの畑には息子とよく通っています。
私は狩猟銃によって大型獣を射殺する事が目的なのです。
こうやって書くと、
遂に荻野も気がふれたか、
と思われても仕方ないでしょうが、
私の思想として
プロセスも出来る限り自分でやらないと美しい料理は出来ない
と思うのです。
アルパインクライマーが美しいラインで自力登攀するのと同じく、なるべく他者や道具や見えない部分を排除し、全て自分の手を使って登ってみたい。
獲物を探し、狙いを定め、引き金を引き、ドドメを刺し、事切れる瞬間を見届け、解体し、あらゆる料理をし、無駄なく食べきる。
これこそが私の中の美しい料理なのです。
意味のない雑草がピロピロしていたり、ドライアイスが出る料理はエンターテイメントとしての料理であって、私の定義する美しい料理ではない。
フランス料理の根幹であるテロワール思想とは、見た目や派手さではなく素材の背景とプロセスです。
獣の胃袋にブルーベリーが入っていれば、ブルーベリーのソースを添える、広葉樹の森の獣ならばその木でスモークをかけ、その土壌から作られたワインを添える。
そうした意味からも現場に行って山の匂いを嗅ぎ、自然に入っていって狩猟によって殺す事、殺して全てを料理して無駄なく食べることはフランス料理の本質であると思うのです。
狩猟獣の山林廃棄問題や害獣駆除問題は完全に都市型生活に慣れた人間がもたらした歪んだ生態系の問題点であり、私にとってあくまでも二次的なもので、これをなんとかしたいから狩猟の世界に入りたい、という綺麗事を言うつもりは毛頭ありません。
そんなモチベーションは続かないですから。
今更ジビエを看板料理に掲げる必要もないでしょう。
私の場合はもっと哲学的なテロワールを突き詰めた問題で
生命とはほかの生命を奪うことでしか、いわば殺す事でしか持続出来ない、という当たり前のことを自分の手で行う事によって美しい料理が完成すると感じているからです。
奪った命を無駄にしないというのは、自分で殺してみて初めて感じることが出来る心境ではないのか。
美しさというのは、殺すことで芽生える命に対する申し訳なさや後ろめたさ、やらなくてもいい殺戮をしてしまった自分の存在意義などをグチュグチュっと混ぜてエスプレッソマシーンでギュと絞り出したような黒光りする人間臭さや手の味や血の匂いではないのか。
命を殺すとはどういうことかをカラダと記憶にタトゥーのように刻み込むこと、それこそが猟銃所持の私の意図です。
殺す事によって得られた命を料理することはエンターテイメントではない。
しかし、矛盾点もあります。
なるべく山に対してフェアでありたいと考えるアルパイン思想においてはハーケンやピトンを使わず、さらにハードコアになればフリーと呼ばれるザイルすらもフェアではないとの思想から使わないツワモノもいます。
ならば、鉄砲で獲物と対峙するのはフェアではないのです。
本当にフェアにやるならば、木の棒とか自作の武器、もしくは素手でタイマンはらなければいけません。
しかし、人間はすでにイノシシやシカに空身では勝てない。山を彼らのように自由に走り回ることすらも二足歩行によって放棄してしまった。
アメリカでは、よりフェアに対峙するために銃ではなくボウガンという弓矢による狩猟もありますが
本来ならば飛び道具など使わずに、もっと手応えが残るものでやらなければいけないのです。金属バットや角材で殴ることによって、なにかを壊すという”手応え”を身体と記憶に残すことこそが本質的なのです。
解体という作業は気持ち悪いとかネガティブなイメージがあるかもしれませんが、わたしがスタッフに解体を教えると、嫌がるかと思いきや、どちらかと言えば嬉々として行われる事が多いです。
血が出て内臓が飛び出し排泄物が漏れ出しながらも皮を剥かれ、骨が外され各パーツに分けられて行くプロセスは人類の歴史における最大の特徴である料理という文化の源流はここにあるのではないかと思うほどに美しい行為です。
そうした一連の流れのずっと下流にこそ、
“美しい料理”
が存在すると感じているのです。