2018年03月10日
凄すぎて絶句

来週木曜日のエンガチョナイトのウサギです。
今週よりも1週間長く熟成されてますので、更に変態臭を放ってます。
おいおい、これ大丈夫かよ。
肉は赤というより黒に近い紫。
ジビエというより生ゴミ。
みなさん、心して臨んでください。
今から走り込みや筋トレとかやって内臓鍛えた方が良いと思います。

2018年03月10日

来週木曜日のエンガチョナイトのウサギです。
今週よりも1週間長く熟成されてますので、更に変態臭を放ってます。
おいおい、これ大丈夫かよ。
肉は赤というより黒に近い紫。
ジビエというより生ゴミ。
みなさん、心して臨んでください。
今から走り込みや筋トレとかやって内臓鍛えた方が良いと思います。
2018年03月09日

花ズッキーニの詰め物いきます。
これは雄しべなので実はありません。
この中にカニのムース詰めます。
あー、良い季節になってまいりました。
人数変更とかでお席少しあります。
レバーで鉄分補給いかがっすか?
ピチピチの牛レバーきました。
山形県の漢方牛という和牛のレバーです。
当たり前ですが、和牛とはいえレバーにはサシなんて入ってないのでゴリゴリの鉄分の塊です。
これは新鮮なウチにムニエルでお出しします。
この週末限定ですかね。
売れ残ったら加熱してパテにします。
脱法レバ刺し感覚で若めのロゼで火入れしますので、サクサク召し上がって下さい。

これは一体…
破壊力抜群…
凄すぎる。
冷たい状態でこれならば、アツアツになるとどうなってしまうのか…
店の空気が重く淀んでますね。
15日の現物が怖い。

マニアックな店にありがちな光景。
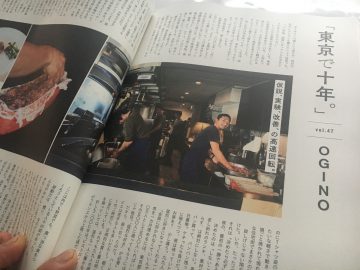
発売中のダンチュウの人気連載に掲載していただきました。
あっという間でもあり、長かったこの10年。
自慢できるような華々しい経歴があるわけでもなく、独立してからも順風満帆ではなかった私の小さなお店、そして自分勝手な使命感に燃えて作ったターブルオギノという兄弟ブランドのストーリーは、まったくもってお恥ずかしいお話ばかりですが、背伸びしても仕方ないので、カッコ悪い事を中心にありのままを書いていただきました。
ご笑覧いただければ幸いです。
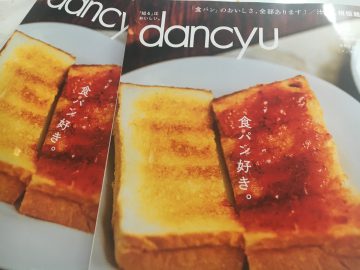
2018年03月07日
明日の第1回エンガチョナイト、満席となりました
ありがとうございます。
絶対満席にならないだろうと高を括ってました。
これだけ酷いこと書けば食欲なんてなくなるだろうと。
そんなことでビビるようでは、エンガチョとは呼べないでしょとばかりにラストスパートで満席となりました。
さあ、明日は下品な一日になりそうです。
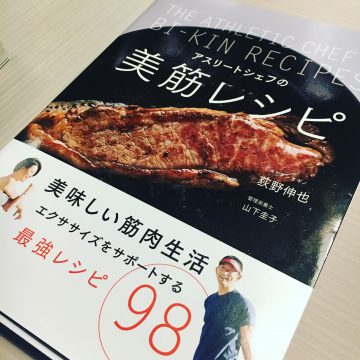
19日にドピュッと発売!
ウチの店でも販売しますんで、是非是非。
ちなみに、前著チキンブレストレシピは台湾で翻訳されることが決まりました。
やったぜぃ
雪山は上級者向け。
そんな怖いイメージでした。
でも、初心者は続けていればいつか中級者となり、いつかのタイミングで雪山デビューもします。
そのタイミングは、どこの山に登ったらとか、何が出来るようになればとか、別にテストがあるわけでもなく、まずは経験するのみ。
しかし、夏山とは装備もまったく異なり、アイゼン含めると片足1キロにもなるため、スピードも上がりません。
足元は昨日降った雨で雪がシャーベット状になっており、所々雪ノ下が小川になっていて腰まで踏み抜いて足はビショビショです。
クレバスとかって、こういうものなんだろうな。怖い怖い。

これが雪の下に埋まってたりするわけです。
もしくは、脆い氷の上が川になっていたりするわけです。
何とか行者小屋に2時間かけて到着。

おおお、赤岳ちゃんよ。
雲ひとつない快晴で、遥か上に見える頂上は、風が巻いているわけでもなく穏やかな表情。
これならいけそうだ。
ピッケルとアイゼンを装着、昼飯食って靴の中で凍った靴下変えて取り付き口から地蔵尾根を直登します。
地蔵尾根は森林限界過ぎたあたりから傾斜がきつくなり、夏に使う鎖やハシゴは柔らかい雪の遥か下です。
もはや雪の壁。
アイゼンを刺して足場を確保するものの、ピッケルはシャーベット状の雪に沈んでしまい使い物になりません。
足元もバラバラと崩れていきます。
うーん、参ったな。
ソロで登っているので引き揚げてもらう事も出来ません。
4点支持で何とか稜線へ。

おう、北アルプス!
最高だ。
が、しかし太陽が出て表面の雪を溶かしていくのがよくわかります。
このまま縦走して赤岳直下の急登は危険だし無理だなぁ
残念ながらここで帰ろう。

来た道を戻るのですが、これが怖い。
テンションのかかり方が登りよりも大きいため、崩れ方が酷い
滑落の7割が下山時というのは、こういうことかと。
行者小屋まで戻って一安心。
いい経験なりました。

こんなんじゃ、谷川岳は遠いなぁ。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 2月 | 4月 » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |