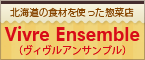2018年01月25日
アンコウの後はクネル行きます。
クネルとはなんぞや。
本来は川魚を使って作るはんぺんみたいなものなんですけど、残念ながらその魚は日本にはいません。
カワカマスと言いまして、カマスみたいな顔した魚ですが、川にいるんです。
小骨が多くて、しかもその骨が複雑な形してるので、フィレに出来ないので練り物用になるパターンです。
で、東京で作るとなると、白身の魚でやるしかありません。
クネルは魚のムースと違って、パナードというシュー生地的なつなぎが入ります。
なので、ニュアンスは硬めです。
しっかりとした歯ごたえあるはんぺんですね。
それを本来はザリガニ風味のベシャメルでグラタンにするんですが、残念ながら日本でザリガニ食う文化が無くて手に入りにくいので、甘エビでいきます。
ザリガニは阿寒湖とかで食用がありますけど、ベラボーな値段なのでウチのガキと捕まえに行った方がいいかもしれません。
ここまでくると原型留めてないやんけ!ってクレーム来そうでビクビクしてますが、そこは長々と書いた言い訳参照。
フランスを代表する巨匠へのオマージュです。
JANコードの更新で売上高に比例して更新料が上がるって、これなんで?
ただ数字配ってるだけで発行や管理は事業者なのに。
そもそも、なんでこんなに高いのかね?
どなたか、この金額の意味について教えてください。
かかりました。
あたーす。
これで第3刷。
料理専門書は2000部売れれば良いところなのに、大健闘してます。
まあ、なかなかあの手の本は日本では無かったですからね。
ちなみにシャルキュトリー教本も韓国で翻訳される事になりそうです。
肉食文化の韓国ならば、あの本から更に進化した素晴らしい肉加工品が出てくるのでしょう。
そんなキッカケにあの本がなれれば幸いです。
おい!
お前は印税生活でウハウハなのだろう!
この下衆野郎!
と、ご意見ありますが、印税だけで生活できるなんてミリオンセラーしない限り絶対無理です。
あと100倍売れれば考えます。
私の出版活動は完全に広告的な意味合いと、そもそも趣味の世界です。
2018年01月24日

テリーヌは水分と脂分とタンパク質の三角形なのです。
このバランスをどうするかってのがオモロイんです。
水分は何を入れるのか、脂は豚なのかフォアグラなのかカモなのか、肉は何をどういうバランスで?
肉も生か焼くか茹でるか、角切りかミンチか?
ほぼ無限に広がります。
それぞれの配合によって出来上がる味わいのバランスを頭の中で計算しつつ、断面を想像して組み上げます。
これがオモロイ。
今回は限界まで水分量を増やしてジューシーな仕上がり。
水分とは酒であり、だし汁を限界まで煮詰めたものをたっぷり加えて、敢えて少し離水するくらいにミキシングを止めております。
繋がりすぎると口当たりが硬く、このジュワッとしたテクスチャーが出ない。
しかし分離気味に作ると、日持ちが圧倒的に短くなります。
これぞガストロノミーのテリーヌ。
久しぶりに作りましたが、やはり良いものです。

旨いキジ料理を喰わせろ予約が入りましたので、嫌々やってます。
胸肉は軽くソテーして骨で取った出汁で煮込んだチリメンキャベツを添えます。
モモ肉は内臓もミンチにしてパテアンクルート。
スカトロフェチの為に火入れはごくごく浅く。
そんでもってメインは産まれたてのイノシシの丸焼き。
いやぁ、変態だわ。

テリーヌ・グルマンドが本日デビューです。
この手のテリーヌは保存目的ではなく、味わいが最優先されます。
味の頂点は作ってから2日目から7日目あたりでしょう。
熟成タイプのテリーヌは作ってから早くて3週間くらいからやっと美味しく食べられます。
そういうテリーヌやるのも面白いかもです。
やりますか。
やろう。
早速材料とって作ります。
デビューは3月中頃か。
2018年01月23日

リヨン料理っぽくて嘘つき野郎クレーム貰いそうな牛タンの塩漬けが完成しました。
リヨンといえば美食というよりもシャルキュトリーの街です。
本当に素晴らしいシャルキュトリーが沢山あり、それを作る国宝級で仕事着にトリコロールをあしらう事を許されたスゲエオジさん達も沢山います。
毛と蹄以外は全て活かし切るという文化の象徴であるシャルキュトリーは私にとって非常にしっくりくる食文化。
フランス食文化の根幹を支えるこの考え方にとても尊敬と共感を覚えます。
ソースクリビッシュというゆで卵とハーブで作られたドレッシングがシンプルに牛タンを旨さを食べさせてくれます。
まだ雪で混乱してるのに、今日からいきます。
お席がダダ空きなので、宜しければ。
まあ、まだ大混乱してる今日にフランス料理を食いたいぜ!って人はあんまりいないと思いますが…
 雛鳥の膀胱包みを始めます。
雛鳥の膀胱包みを始めます。
ヴェッシーと言います。
オシッコ溜めてる臓器に鳥を詰めて縛って火入れするのです。
真空パック的意味合いと圧力鍋的な意味合いがありますが、独特の香りも相まって、最新機材ではこの味わいに変えられるもののない古典料理です。
たまたまリヨン郊外のお店で作られることが多かった料理ですが、別にリヨン料理ではありません。
たしかにリヨンは内臓料理が豊富にありますが、地方料理として確立してるのでもないですからね。
膀胱を肉やレバーのペースト詰めたソーセージなどは各所にあり、特にドイツ系に多いです。
日本ではなかなか手に入らない膀胱でしたが、私が芝浦の屠殺場にお願いして流通させてもらいました。
まだまだこういうモノって日本には沢山あります。

テリーヌ・グルマンド仕込んでます。
トリュフ、フォアグラ、鴨、鹿、銘柄豚を8センチの断面に注ぎ込みました。
圧倒的なトリュフの香り、ゴロゴロ入ったフォアグラ、大ぶりにカットして味わいを引き出した肉。
肉を焼くのと同じく、ロゼに火入れしたテリーヌは保存食ではなく、完全なるガストロノミーです。
ウチのアミューズでターブルのテリーヌを色々味わって貰ってますが、このテリーヌは手捏ねでザックリとしたダサい仕上がりです。
その方が肉の味わいはエッジが効いてきます。
万人ウケしないのですが、ウチみたいなエッジの立ったお客さんにはこのくらい破壊力あるほうが良さそうなので、自分で作る事にしました。






 雛鳥の膀胱包みを始めます。
雛鳥の膀胱包みを始めます。