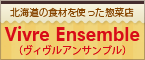2010年06月10日
表現の自由とは・・・
6月9日、ロックの日。
またの名をアイナメの日。
これもある意味では表現の自由。
しかし、人を傷付けるのも表現の自由でしょうか。
ザ・コーブという映画が物議を醸しております。
和歌山県のイルカ漁を批判的に描いたドキュメンタリー映画で、アカデミー賞をとったとか。
それがどうした。
アカデミー賞は免罪符でしょうか。
本来見てから議論すべきでしょうが、相次ぐ上映中止で見たくても見れません。
オーストリアのドキュメンタリー映画で“命の食べ方”というものがありました。食材を生産する現場を説明も字幕なく、ただただ豚や牛の屠殺される場面や、機械的に処理される鶏や魚を映し出しています。そこには否定も肯定もありません。
作者の意図としては、パックになるまでの命の扱い方を見て知ってほしい、そして考えてほしい、とのことだと思います。
これはフェアな表現。
しかしながら、このザ・コーブというのは恐らく違ったつくりになっていると思われます。
海中でイルカを屠殺するために入江が真っ赤に染まるとか、船でひっぱりまわすとか・・・
はたして首から血を抜かれ、鎖にぶら下げられ、内臓を引っ張り出され、挙句の果てにチェンソーで真っ二つにぶった切られる牛や豚はいいのでしょうか。
フランス料理のジビエは秋の風物詩なんでしょうか。
カンガルーや猿を食べる国は同じ観点から見ても映画の題材にならないのでしょうか。
和歌山のイルカ漁だけを切り取って議論の的にするのはおかしいのではないでしょうか。
偏ったとらえ方で食文化を取り上げるのは、明らかにフェアじゃありません。伝えるほうは表現の自由でも伝えられるほうは表現の自由も手段も持ちません。
人間は如何に罪深い生き物なのか、しかしながら食べなくては生きていけない現実。
だからこそ、ありがたく頂戴し、無駄を出さない努力を怠らないことが美食、飽食の現代の食文化に最も欠けていて、必要なことだと私は考えます。
この題材はウチの賄いの時間にスタッフ同士で話し合います。
6月9日
孤高のメス
坂本竜馬が
どうせ人間死んだら土に還るんだし、やりたいことを思いっきりやったらいいんですよ。
と、言っていたそうな。
さすがに土に還る前に他の人の役に立てるとまでは坂本竜馬も予想できなかったでしょう。
孤高のメス、見てきました。
死ぬこと、そして生きること。
脳死患者と、その肝移植を待つ患者。
消えそうな命の火が、再び違う形で灯を保ちます。
たとえそれが違法だとしても、その医者は目の前の命に向き合います。
そんな映画でした。
来月、改正臓器移植法が施行されます。
本人の意思が不明でも家族の同意があれば移植手術が可能になるそうです。免許証の裏に張るアレですね、意思表示カード。
ちなみに私はある臓器を除いて、すべて提供するつもりです。バラバラにしてください。使えればですが・・・
医療の進歩によって一昔は助かる見込みのなかった病気が助かるという現代。しかしながら人間いつ死ぬのかだけは誰にもわかりません。
あるお母さんが、不幸にも余命三カ月を宣告され、小学生にあがる前の一人娘をこの世に残していかなくてはならない状況で、娘に何を教えたか・・・
それは、ご飯の炊き方と、買い物の仕方だったそうです。
そしてその女の子はお母さんが亡くなった翌日からお父さんに夕食を用意したんだそうです。
そんな話が思い出されます。
食というのは命と切っても切り離せないものであります。
それに携わる私どもが、いまの子供たちに何ができるのか・・・
多分、私の薄汚れた内臓よりもいいものを残してあげられるはずです。